ブログ
生産管理システムはなぜ高額になるの?費用の内訳と削減方法
生産管理システムはなぜ高額になるの?
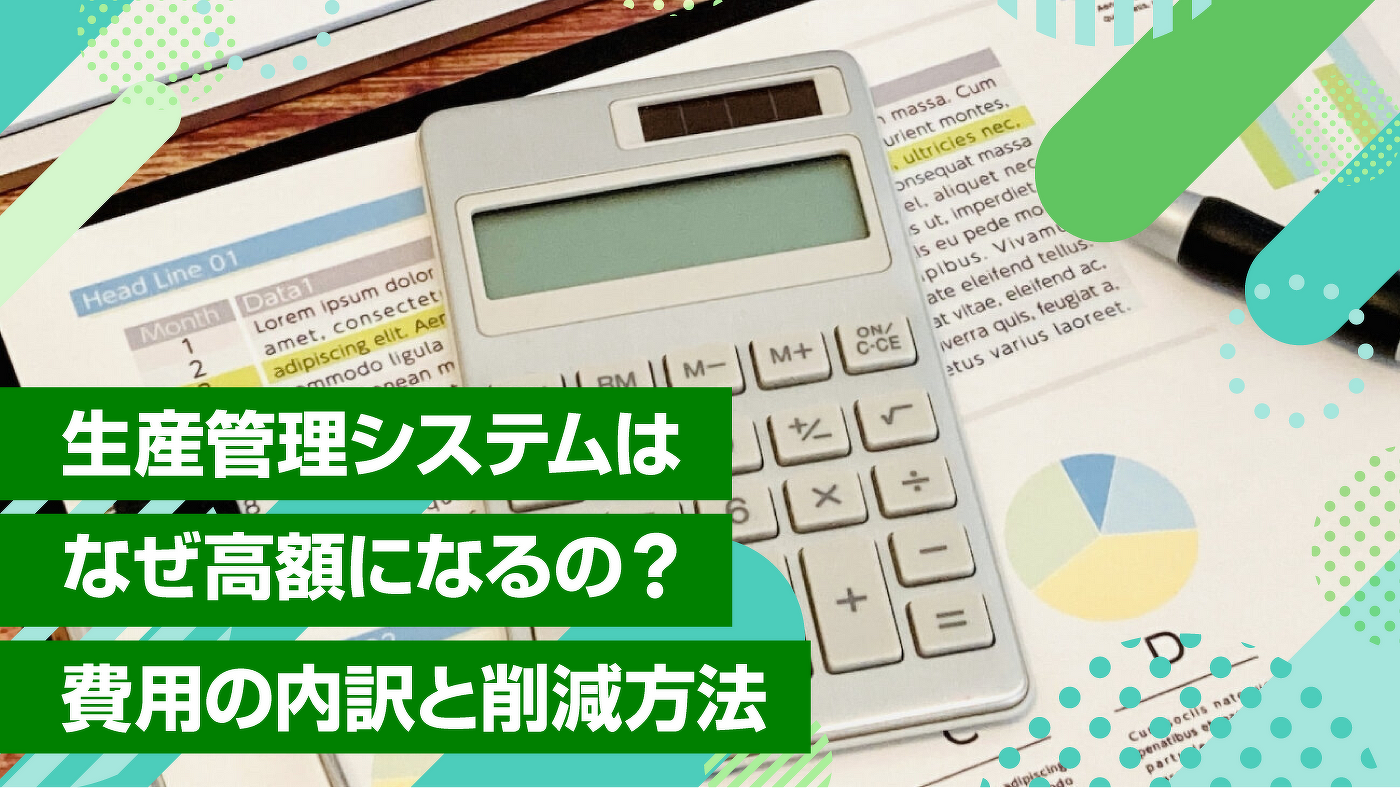
生産管理システムはなぜ高額になるの?
「生産管理システムの見積もりを取ったら、想像以上に高額で驚いた…」
「なぜこんなに費用がかかるの?」
こうした疑問は、製造業の経営者や管理者であれば一度は抱いたことがあるはずです。
生産管理システムの価格は、数十万円から数千万円までと幅が広く、見積書だけでは妥当性を判断しづらいのが実情です。この記事では、なぜ生産管理システムが高額になるのか、その理由と費用を抑える方法をわかりやすく解説します。
なぜ高い?生産管理システムが高額になる5つの理由
生産管理システムが高額になるのにはわけがあります。
例えば、「専用の機械を製造する過程」を想像してみてください。用途や効果のヒアリングから始まり、設計、部品の製造・検査、ユニットの組み立て・検査、全体の組み立て・検査、テスト……多くの工程を経て機械が完成します。小さな機械でも1,000万円ほどかかってしまうのは、このプロセスがあるからですよね。
システムの構築もプログラムという形で、同じようなプロセスを経て、膨大な作業が行われています。ここでは、コストがかかる代表的な5つの要素を見ていきましょう。
理由1:開発・カスタマイズ費用
ゼロから作るシステムは、設計から開発、テストまで専門エンジニアが長期間かけて取り組みます。エンジニアの人件費は低くても年収600〜1,000万円クラス。開発期間も1〜3年かかることがあります。
製造業は業種ごとに業務フローが違うため、カスタマイズが必要になり、さらに費用が増えます。既存システムとの連携も工数がかかるポイントです。
例:基本システム500万円+カスタマイズ300〜1,000万円=合計800〜1,500万円
理由2:サーバー・インフラ費用
オンプレミス型(自社にサーバーを置く方式)では、サーバーやネットワーク機器など物理的な設備が必要になります。そのため、購入から設置工事まで、初期費用が必要です。さらに、データセンターでの運用費や定期的なハード更新など、維持費も発生します。
| 費用例 | 内訳 |
|---|---|
| 初期費用例 |
|
| ランニングコスト例 |
|
※当社ヒアリングデータに基づく
クラウド型ならこの部分を大きく削減できますが、代わりに月額料金が継続的にかかります。
理由3:営業・販売コスト
システムの販売には、知識のある営業担当やSEが何度も訪問する必要があります。1件成約までに10〜20社を回ることも珍しくなく、その活動費や失注分のコストも価格に反映されます。
展示会やセミナー、全国拠点の維持費もあり、営業体制そのものが最終価格を押し上げる一因です。
理由4:保守・サポート体制
「導入したら終わり」ではなく、使い続けるためのサポートも費用に含まれます。24時間対応のコールセンターや、全国への技術者派遣、法改正対応のアップデートなどがその例です。
保守費はシステム価格の15〜20%が目安であることが多いです。加えて、バージョンアップや緊急対応は都度費用がかかる場合があります。
理由5:機能の複雑化と高機能化
最近の生産管理システムは、工程管理や原価計算、品質管理、在庫管理、各種帳票の発行、レポート機能、他システムとの連携など、幅広い機能を備えています。
機能が増えるほど開発コストも上がり、使わない機能にも保守費を払うことに。また、操作が複雑になり、トレーニングコストも上がります。必要な機能を見極めましょう。
機能別コスト例
- 基本的な生産管理 300万円
- 原価管理機能 200万円
- 品質管理機能 150万円
- 在庫管理機能 100万円
- 各種連携機能 300万円
※当社ヒアリングデータに基づく
このように、カスタマイズや必要なハードに応じて生産管理システムのコストは膨らむ傾向です。自動車のように基本仕様の規格品をそのまま購入すればコストを抑えられ、カスタマイズや機能が増えれば、それだけ高額になります。
価格帯別に見る生産管理システムの特徴
生産管理システムは、金額によって使える機能やサポート内容が変わります。ここでは、それぞれの価格帯ごとの特徴と、向いている企業規模や用途を解説します。
高額システム(1,000万円以上)
もっとも高額なのは、大手ベンダーが提供する統合型システムです。ERP(基幹システム)とも呼ばれ、生産管理だけでなく、販売、購買、在庫、会計まで全てをカバーします。大企業や工場が複数ある企業に多く導入されています。
メリットとデメリットは次の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
代表的な提供企業の一例として、SAPやOracleが挙げられます。その他、大手国産ベンダーの統合型システムもこれにあたります。
中価格システム(500〜1,000万円)
中価格帯の生産管理システムは、中堅ベンダーが提供するパッケージ型が中心です。業界特化型が多く、必要な機能だけを選んでカスタマイズできるのが特徴です。中規模工場や特定業種に適しています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
スペックと価格のバランスが良い一方で、将来的な機能追加や他システムとの連携に制約が出る可能性があります。導入前に中長期の運用計画を立てておくことが重要です。
低価格システム(100〜500万円以下)
低価格帯の生産管理システムは、クラウド型やSaaS型が多く、標準機能に特化しています。月額課金制で利用できるシステムも多く、初期費用を抑えつつ短期間で導入が可能です。小規模な町工場に向いています。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
クラウド型システムは、月額5〜20万円、初期費用として0〜100万円程度が相場です※。
※ https://it-trend.jp/production_management/article/comparison-system
エムネットくらうどは低価格帯でありながら、町工場の現場から生まれたシステムならではの使いやすさと、iPad対応による導入のしやすさが強みです。必要機能に絞ったシンプル設計で、短期間・低リスクの導入を実現します。
見積もりに含まれない「隠れたコスト」に要注意
見積書に載っている金額だけで「安い」と判断すると、あとで思わぬ出費に驚くことがあります。データ移行や教育研修、運用中の追加開発など、導入後に出てくる「隠れたコスト」も把握しておくことで予算超過を防げます。
導入時の隠れたコスト
新しいシステムをスムーズに使い始めるためには、環境を整える準備が必要です。例えば、次のようなコストが追加になります。
- データ移行費用:既存データを新システム用に変換・整備
- 教育・研修費用:管理者向け・現場スタッフ向けの研修、マニュアル作成
- 環境整備費用:PCやタブレット、バーコードリーダーなど周辺機器の追加購入
運用開始後の隠れたコスト
システムを使い始めた後も、想定外の出費が発生することがあります。新機能の追加だけでなく、契約更新時の保守費用改定や、日々の運用を維持するための人件費などが含まれます。
またクラウドシステムでは、少ないID数で見積もりを依頼したばかりに、必要なIDが増え、結果的にコストが高くなるケースも散見されます。将来的に必要になるID数を見越して、見積もりを依頼すると安心です。
- 追加開発費用:新機能の追加やレポートのカスタマイズ、連携システムの追加
- 保守費用の値上げ:契約更新時に料金改定やサポート範囲縮小が行われるケース
- 内部運用コスト:システム管理者の人件費、バックアップやメンテナンス作業
- オプション費用:オプション機能の追加
- ID数に伴うコスト:必要なIDの数で変動(クラウドシステムの場合)
解約時のコスト
契約を終了する時にも、費用が発生することがあります。
- データ取り出し費用:データのエクスポートや形式変換
- 契約解除料:中途解約に伴う違約金や残リース料の一括支払い
- 撤去費用:機器の撤去・廃棄やデータ消去対応
見積もり段階で「導入時・運用中・解約時にかかる費用」をベンダーに具体的に確認しておけば、安心して契約を進められます。
生産管理システムのコストを抑える5つの方法
高額になりがちな生産管理システムですが、できる限りコストは抑えたいものです。ここでは、導入前から実践できるコストを抑える5つの方法を紹介します。自社の状況に合うものを組み合わせて、予算オーバーを防ぎましょう。
方法1:クラウド型システムの選択
初期費用を抑えたいなら、サーバーを持たないクラウド型システムが有力候補です。サーバー管理や保守が不要で、自動バージョンアップも受けられます。
クラウド型システムには、比較的安価な月額費用はかかり続けます。一方で、オンプレミス型システムは買い切り型ですが、5年周期ほどでハードウェアの老朽化による再購入(リプレイス)が必要で、月額や年額で保守費用も発生します。
こうした費用含めて比較すると、コスト面ではクラウド型システムが優位といえます。
費用比較例(3年間)
| 導入方式 | 初期費用 | 年間費用 | 3年間の総費用 |
|---|---|---|---|
| オンプレミス型 | 1,000万円 | 100万円 | 約1,300万円 |
| クラウド型 | 50万円 | 120万円 | 約410万円 |
方法2:段階的導入でリスク分散
一度に全機能を入れず、必要な範囲から始める方法もひとつの手です。
たとえば、まず工程管理だけを導入し(約50万円)、現場が慣れてきたら在庫管理機能を追加(約30万円)、さらに必要に応じて原価管理機能を追加(約40万円)といったような導入の仕方です。
初期投資を抑えつつ、現場が慣れてから範囲を広げられるため、導入失敗のリスクも下げられます。
方法3:標準機能中心の運用
カスタマイズを最小限にとどめ、業務をシステムに合わせる運用方法もコストを抑制できます。
標準レポートを活用し、外部連携は最小限に抑えるといった工夫により、導入費用や保守費用を削減できる可能性が高まります。導入期間の短縮にもつながります。
方法4:複数社での相見積もり
生産管理システム導入時にコストを抑えるには、同じ要件を複数ベンダーに提示し、見積もりを比較します。
その際、単価の安さだけではなく、システム導入後に発生しやすい追加コストも含めた総所有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)で評価しましょう。
方法5:補助金・助成金の活用
国や自治体の制度を利用すれば、数百万円単位で負担を減らせます。代表的な制度は、次の通りです。
対象システムには制限があり、申請には事前準備が必要です。導入計画と合わせて、申請書類の準備を進めましょう。
これが適正価格!判断基準とチェックポイント
生産管理システムの価格は幅が広く、安ければ良い、高ければ安心とも限りません。自社にとっての「適正価格」を見極めるには、企業規模や必要な機能、運用体制を踏まえて総合的に判断することが大切です。
企業規模別の適正価格目安
以下は企業規模ごとのおおよその費用感です。
| 企業規模 | 年間費用目安 | 初期費用目安 | 月額費用目安 |
|---|---|---|---|
| 小規模企業(従業員10名以下) | 50〜150万円 | 0〜100万円 | 5〜12万円 |
| 中規模企業(従業員11〜50名) | 100〜300万円 | 50〜200万円 | 10〜25万円 |
| 大規模企業(従業員51名以上) | 300万円以上 | 200万円以上 | 25万円以上 |
※当社ヒアリングに基づく
また、「年商に対する1%」をデジタル化予算とする考え方もあります。自社の人数や年商規模と照らし合わせながら参考にしてください。
価格妥当性のチェックポイント
適正価格かどうかを見極めるには、以下の観点で確認しましょう。
- 機能と価格のバランス
- 将来の拡張性
- サポート体制
- 投資回収期間
まずは、必要な機能がきちんと揃っているか、逆に不要な機能で価格が上がっていないかを確認します。次に、将来の拡張性として、事業拡大や拠点追加などに柔軟に対応できるかを見ておきましょう。
サポート体制は、導入時だけでなく運用開始後もどこまで支援してもらえるのか、緊急時の対応があるかが重要です。そして投資回収期間は、人件費削減や業務効率化の効果を考慮し、おおむね2〜3年以内に回収できるかを目安に判断します。
まとめ:適切な価格で最適なシステム選択を
生産管理システムが高額になる背景には、開発やカスタマイズ費用、サーバー・インフラの準備、営業やサポート体制、そして機能の複雑化があります。こうした理由を理解しておくと、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。
生産管理システムの選定ポイントは次の通りです。
- 自社に必要な機能を明確化
- 段階的導入でリスク分散
- クラウド型で初期費用削減
- 隠れたコストも含めて比較
- 投資回収期間を必ず計算

- 初期費用が低価格
- オプションは現時点で2種類のみ
- オプションは費用はイニシャルで、追加したとしてもランニングコストは変わらない
- 10ID分が標準利用IDとしてセット価格になっており、追加IDは1ID単位で追加でき標準セット価格より安価に設定されているので増える場合も検討しやすい
- 保守費用が利用料に含まれているので別途発生しない
- カスタマイズをすることなく利用するので追加費用が発生しにくい
- サーバーのリプレイスなどもないため、月額費用のみで使い続けられる
- 問合せ窓口なども設置されているので、電話やメールでの問い合わせなら追加費用も発生することなくサポートが受けられる
これらの理由から低コストだけでなく、使い続けられる様々なメリットが考えられた料金設定となっています。
近年は初期費用を安くして、運用が定着してくると追加コストがかかるような料金設定も増えてきているので要注意です。
この記事の監修者

角野 嘉一(かどの かいち)
日本ツクリダス株式会社 代表取締役 / エムネットくらうど プロダクト責任者
前職において父親の経営する鉄工所でデジタル化を推進し、業務効率化とネット集客の両面から改善を行うことで、売上高200%アップを達成。その経験を土台に、2013年に独立して日本ツクリダス株式会社を創業した。金属加工業務と並行して、町工場でも使いやすい納期・工程管理システム「エムネットくらうど」を開発し、2025年現在では約170社が利用するサービスへと成長させている。
製造現場での20年にわたる実務経験に加え、DX・生産管理の両面に精通した専門家として注目され、テレビ、雑誌、Webメディアなどからの取材も多数あり、製造業界専門誌への寄稿実績もある。デジタル化の取り組みが評価され、2021年 全国中小企業クラウド実践大賞 近畿大会「近畿総合通信局長賞」、2024年 経済産業省「DXセレクション」優良事例企業に選出された。
著書『マンガでわかるやさしいDX デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本』では、現場で培った改善ノウハウを体系化。本記事でも、自身の経験と知見をもとに、町工場の現場で本当に役立つ生産管理とDXのポイントをわかりやすく解説している。