ブログ
生産管理システムとは?町工場社長のための基礎講座
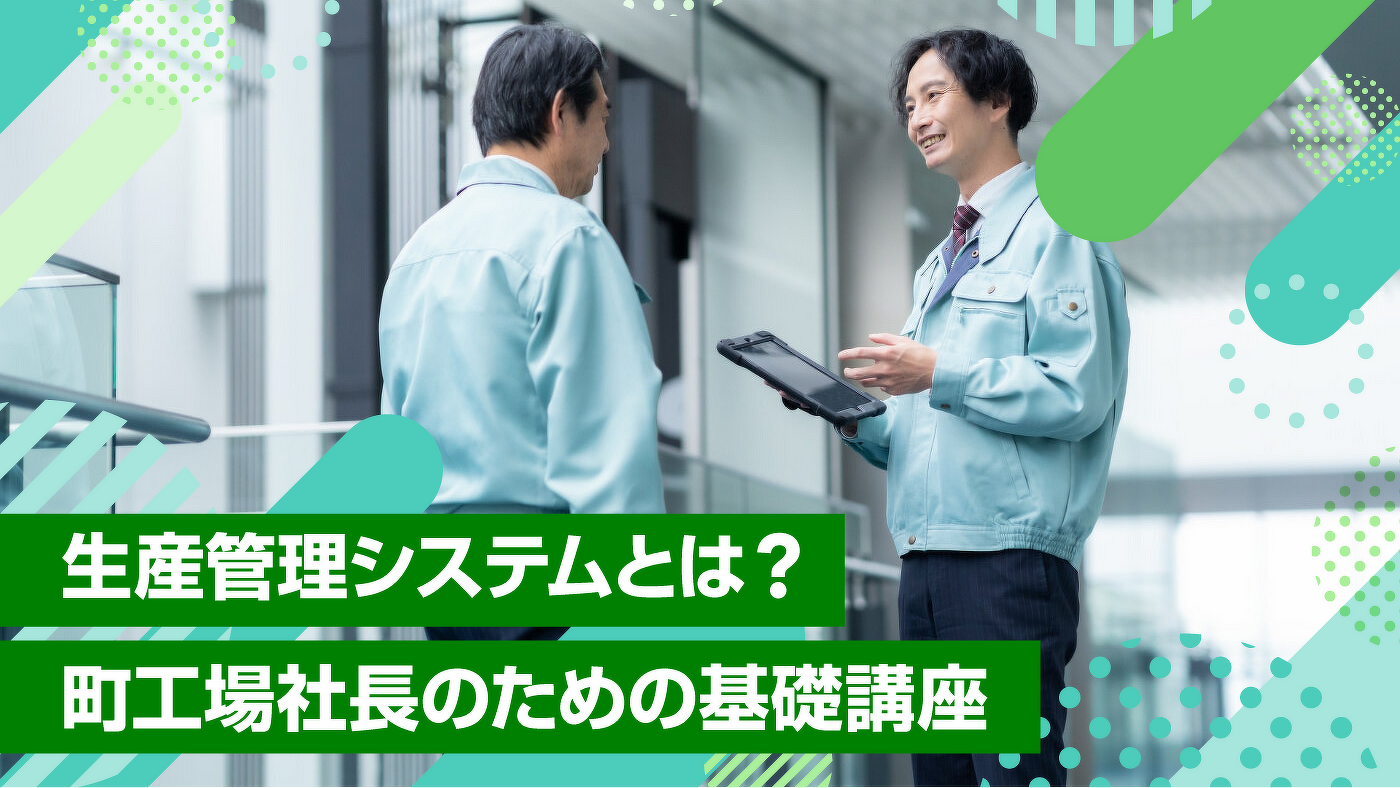
「生産管理システムって聞いたことはあるけど、正直よくわからない...」 「うちみたいな小さな町工場には関係ない話じゃないの?」
そんな風に思っている町工場の社長さんは多いのではないでしょうか。
この記事では、生産管理システムの基礎知識から導入メリット、選び方まで、町工場の社長さんが知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。
生産管理システムとは?基本知識を理解しよう
そもそも生産管理システムとは、どのような役割を担うのでしょうか。まずは、その概要を掴みましょう。
生産管理システムの定義
生産管理システムは、「いつ・どこで・何を・どれだけ作るか」を効率よく管理するためのツールです。
工程、在庫、納期、品質、原価など、製造業に関わるさまざまな情報をまとめて管理します。
紙やExcel、口頭での伝達、人の記憶に頼っていた仕組みを、誰でも・すぐに・正確に確認できるかたちに変えていくのが生産管理システムの役割です。
従来の管理方法との違い
例えば、ホワイトボードに作業予定を書き出し、材料の在庫は担当者の経験と記憶で把握。
受注データはExcelで集計し、完成報告は紙で提出するーー町工場ではよくある、慣れ親しんだスタイルです。
しかし、情報の更新や検索、集計に手間がかかるうえ、必要な情報がバラバラに点在しているぶん、現場全体の流れが見えづらくなります。
生産管理システムを利用すれば、こうした情報が一つにまとまり、確認・判断・修正までのスピードが向上します。従来の管理方法との違いを実感できるはずです。
生産管理システムのメリット
生産管理システムを利用する最大のメリットは、「現場の今」が正確に見えることです。
作業の進捗、材料の不足、設備の空き状況。これらをすぐに把握できれば、顧客対応も早くなります。
また、紙への記載や集計作業の負担が軽くなり、事務所の管理業務にも余裕が生まれるでしょう。過去のデータをもとに改善を進めたり、原価の見直しを行ったりする作業も、やりやすくなります。
生産管理システムの主な機能を知ろう
生産管理システムにどんな機能があるのかイメージしにくい方もいるかもしれません。この章では、システムに搭載されている主な機能を紹介していきます。
受注管理機能
受注管理機能は、お客様からの注文情報をもとに、納期や製造スケジュールを自動で計算してくれる機能です。注文内容や数量、納品日などをシステムに入力することで、「注文書が見つからない」といったトラブルを防ぎ、工程や材料の準備を効率化します。
見積書や注文書の作成も、フォーマット化されているため、事務作業の効率化が可能です。システム内には売上データが蓄積され、忙しい月や得意先の傾向もあとから確認できるようになります。
工程管理機能
工程管理機能は、「今どの作業がどこまで進んでいるのか」現場の流れをリアルタイムで把握できる機能です。
作業ごとの進捗状況はもちろん、設備や人の稼働状況もひと目で分かるため、手待ち時間や作業の遅れも「見える化」されます。作業指示書の自動生成機能により、伝達ミスの防止にもつながります。現場の流れを止めずに、次の作業へスムーズに引き継ぐ環境を整える機能です。
生産管理の中でもエムネットが一番得意なことです。その工程いつまで?どこまで進んでいる?、次は誰?などこれが見える化されるだけでも大きなメリットが得られます。
在庫管理機能
在庫管理機能は、材料や部品、完成品の在庫数をリアルタイムで管理できる機能です。
入庫や出庫の記録も自動で反映されるため、在庫台帳の記入や二重チェックといった作業を削減できます。
「いつ」「誰が」作った在庫が、「どこに」「いくつ」保管されているか情報として管理することで、トレーサビリティの確保も可能です。無駄な在庫や欠品の予防にも役立ちます。
品質管理機能
品質管理機能は、製品が決められた基準を満たしているかどうかを確認した結果を記録しておく機能です。
検査内容や結果、不良が出た際の原因もデータとして残せるため、改善活動のベースにもなります。「どこで不良が出やすいか」「なぜ不良が出たのか」といった分析ができるようになれば、再発防止にもつなげやすくなります。
エムネットなら外部アプリとの連携で出荷前の製品写真を残したり、不良品の記録や検査内容を保存したりなど様々なことが可能になります。
原価管理機能
ものづくりにかかるコストを細かく把握できるのが、原価管理機能です。
材料費や人件費、電気代などを含めた「実際にかかった原価」を、製品別・工程別に集計することができます。
利益率の見直しや、価格設定の検討にも役立つため、原価をもとにした価格交渉やコスト改善の根拠として活用できます。どこにどれだけコストがかかっているかを可視化できる点は、町工場にとって重要なポイントです。
レポート・分析機能
これまで紹介した各機能の情報をもとに、自動で帳票を作成したり、グラフやチャートで見える化したりできる機能です。
「今月の受注実績」「スタッフごとの生産性」など、知りたい視点にあわせた出力が可能です。
過去の実績や傾向をもとに経営判断ができるようになれば、事業の成長につながっていきます。
生産管理システムの種類と特徴
生産管理システムに限りませんが、システムの種類は「クラウド型システム」と「オンプレミス型システム」に分かれます。
導入方法や運用スタイルによって、自社に合うシステムを選ぶことが重要なポイントです。この章では、それぞれの特徴と向いている企業の傾向を紹介します。
クラウド型システム
クラウド型システムは、インターネットを通じて使うタイプのシステムです。
自社に専用のサーバーを持つ必要がなく、PCやiPadからログインするだけですぐに使えます。現場、事務所、自宅など複数拠点からアクセス可能です。
サービス提供企業が自動でバージョンアップを行うため、IT担当者がいない会社でも扱いやすい特徴もあります。月額課金制が一般的で、初期費用を抑えやすく、小規模事業者から始めやすいシステムです。
オンプレミス型システム
オンプレミス型システムは、自社のサーバーにインストールして使うタイプのシステムです。
多くの場合、初期費用としてライセンスをまとめて購入するため、導入時のコストは高めですが、長く使うほど割安になるケースもあります。
自社専用の環境を構築できるため、細かいカスタマイズにも柔軟に対応しやすい一方で、社内に管理できる人材や体制が求められます。
セキュリティを自社で担保したい、社外にデータを置きたくないというニーズがある企業に向いています。
町工場に適したシステムの選び方
製造業向けのシステムには選択肢が多く、操作性もコスト感もさまざまです。この章では、町工場が生産管理システム導入を検討する際に押さえておきたい選び方と失敗しない選定の進め方を紹介します。
選定時の重要ポイント
生産管理システム選定時に押さえておきたい重要なポイントは以下のとおりです。
1. 操作の簡単さ
町工場のシステム選定では、現場のスタッフが毎日使うことを前提に考えなければなりません。直感的に操作できるシステムかどうかを重視しましょう。
- ボタンや機能が最小限である
- 画面が見やすい
- メニューが整理されている
このように、マニュアルを見なくてもある程度使える設計であれば、現場にスムーズに浸透しやすくなります。
直感的な感覚って実はとても大切です。見た目の分かりやすさでシステムに取り組もうとする気持ちが大きく変わります。
エムネットくらうどは、実際に見て頂いたお客様から「見やすい」という評価を頂けることがとても多いソフトです。
2. 段階的導入への対応
最初からすべての機能を使いこなすのは、どの現場にとってもハードルが高いものです。
はじめは必要最小限の機能だけを使い、慣れてきたら少しずつ広げていく。そんな段階的な導入に対応できるシステムが理想的です。
無理に一気に変えようとすると、現場の混乱や反発を招くこともあります。
小さくスタートし、効果を実感しながら、徐々に運用範囲を広げていける仕組みが望ましいでしょう。
これも実は大事だけどシステムの仕組み上できないことが多いのが現状です。エムネットくらうどでは、段階的な導入も問題なく対応できます。
3. コストパフォーマンス
予算には限りがあります。だからこそ、費用対効果はシステム選定時に確認しておきたいポイントです。
チェックすべきなのは、初期導入費用だけでなく、月額料金や保守費用、カスタマイズの有無、解約時の条件などです。システムによって料金体系が異なるため、「最初は安くても、後から思った以上に費用がかかった」というケースもあります。
4. サポート体制
「導入して終わり」ではなく、「導入後にどれだけ寄り添ってもらえるか」も大事な選定基準です。
- 初期設定の支援
- 現場向けの研修
- トラブル時の問い合わせ窓口
- バージョンアップ時のフォロー
こうしたサポート体制の手厚さがあれば、使い続けるうえで安心感につながります。
失敗しない選び方の手順
生産管理システムの導入を成功させるには、システム選びの流れも重要です。ここではステップごとに失敗しない生産管理システムの選び方を解説します。
ステップ1:現状の課題整理
まずは、何に困っていて、どこを改善したいのかを言語化することから始めます。
在庫管理なのか、工程の見える化なのか。優先順位をつけておくと、生産管理システムの比較もしやすくなります。
あわせて、導入にかけられる予算も設定しておきましょう。
ステップ2:情報収集
次に、複数のシステムを比較します。カタログやWebサイトだけでなく、同業他社の導入状況も参考にしてみてください。
展示会や無料セミナーに参加して、実際に触れてみるのも有効です。
ステップ3:実際の確認
気になるシステムが見つかったら、デモを見せてもらったり、無料トライアルで実際に操作してみたりするとよいでしょう。
現場のスタッフにも使ってもらい、「これなら続けられそうか?」「使ってみてどうか」と意見をもらうことが大切です。
ステップ4:導入計画の策定
そして、導入前にスケジュールを整理します。
いつ、誰が使うのか。操作説明や社内研修はどうするか。また、効果測定はどのように行うか。
あらかじめ計画を立てておけば、現場への負担を最小限に抑えることができます。
生産管理システム導入時の注意点
どれだけ良いシステムを選んでも、導入の仕方次第で使われない仕組みに終わってしまうケースがあります。この章では、導入時によくある失敗と対策、そして成功に向けた準備のポイントを解説します。
よくある失敗パターン
システム導入時のよくある失敗パターンは以下のとおりです。
1. 機能重視での選択
「高機能なほうが便利に使えるはず」と思って、機能を盛り込んだ結果、使いこなせずに終わってしまうケースがあります。せっかくのシステムも、現場で使われなければ意味がありません。
<対策>
本当に必要な機能に絞り、自社に合ったシステムを選ぶことが大切です。
2. 現場への説明不足
現場の理解が得られないまま導入を進めてしまうと、抵抗が生じます。「余計に仕事が増えた」「また面倒なことをいい始めた」と感じさせてしまうケースも少なくありません。
<対策>
導入前には、なぜこのシステムが必要なのか、どんなメリットがあるのかをしっかり共有しましょう。合意形成が必要です。
3. 一度に全機能導入
すべての業務を一気にシステム化しようとすると、現場の混乱を招きます。アナログ管理に慣れていた場合、最初からフル機能で運用するのは現実的ではありません。
<対策>
まずは一部の機能から使い始め、徐々に活用範囲を拡げていきましょう。
4. 投資対効果の未確認
「なんとなく便利そうだから」「他社も使っているから」という理由で導入すると、何が改善されたのか、費用対効果が分からないままになりがちです。
<対策>
事前に「何を改善したいのか」「導入によってどのように変わったか」を測る指標を決めておけば、費用対効果が明確になります。導入後の見直しや改善にもつながりやすくなります。
成功のための準備
ここまで解説してきたように、導入をうまく進めるには、準備が欠かせません。
まずは、業務フローなどの現状を把握しておきましょう。どこにムダがあるか、誰の手に頼っているかが見えてくると、システムに何を期待すべきかもはっきりします。
また、導入はひとりで進めるのではなく、社内で役割を分けてチームで進める形が理想です。
あわせて、現場が戸惑わないように、教育や研修を計画しておきましょう。
まとめ:生産管理システムで製造業の効率化を実現
生産管理システムは、町工場のような小さな現場でも効果を実感しやすいツールといえます。最後に、導入成功のための要点を改めて確認しておきましょう。
- 現状の課題を明確化してからシステム選択
- 操作の簡単さを重視した選定
- 段階的導入で現場の理解を得る
- 継続的なサポート体制の確保
いまのやり方に限界を感じているなら、まずは情報収集から始めてみませんか?自社に最適な生産管理システムを見つけてください。
この記事の監修者

角野 嘉一(かどの かいち)
日本ツクリダス株式会社 代表取締役 / エムネットくらうど プロダクト責任者
前職において父親の経営する鉄工所でデジタル化を推進し、業務効率化とネット集客の両面から改善を行うことで、売上高200%アップを達成。その経験を土台に、2013年に独立して日本ツクリダス株式会社を創業した。金属加工業務と並行して、町工場でも使いやすい納期・工程管理システム「エムネットくらうど」を開発し、2025年現在では約170社が利用するサービスへと成長させている。
製造現場での20年にわたる実務経験に加え、DX・生産管理の両面に精通した専門家として注目され、テレビ、雑誌、Webメディアなどからの取材も多数あり、製造業界専門誌への寄稿実績もある。デジタル化の取り組みが評価され、2021年 全国中小企業クラウド実践大賞 近畿大会「近畿総合通信局長賞」、2024年 経済産業省「DXセレクション」優良事例企業に選出された。
著書『マンガでわかるやさしいDX デジタルとアナログを融合し、仕事の効率化を目指す本』では、現場で培った改善ノウハウを体系化。本記事でも、自身の経験と知見をもとに、町工場の現場で本当に役立つ生産管理とDXのポイントをわかりやすく解説している。
